「『塚本詩織』かぁ…」
放課後。僕は教室で一人、女の名を呟いていた。塚本詩織は今日のターゲットだ。今日は珍しくも、催眠にかけるターゲットは事前に決めてあった。いつもならば、校内を歩き回ったりなどして、偶然出会った女を催眠にかけることが多かったが、今回はそうではない。
たまには違ったアプローチをしてみるのもいいと思っただけだが、今まで催眠にかけてきた女たちに、催眠にかけるのにちょうど良さそうな子を紹介してもらったのだ。今回はその中でも『塚本詩織』という女にターゲットを絞った。写真で確認させてもらったが、塚本さんは美人であることは当然のことながら、勝気で頼れる性格らしく、催眠にかけるにはもってこいの女だ。
「それにしても良さそうな女を紹介してもらったな」
スマホに保存した写真を眺めながら、口角を上げる。小柄な体形だが、気が強そうな女だ。僕は心を躍らせながら、塚本さんが教室を訪ねてくるのを待っていた。
「そろそろ来るはずだな」
塚本さんを紹介してくれたのは以前催眠にかけた高橋夏海だ。高橋さんに塚本さんを呼び出してもらっている。塚本さんは高橋さんが待っていると思い込ませて、警戒心を解く。僕はといえば、高橋さんが待ち合わせ場所に指定した教室で待っているというわけだった。
「夏海ちゃん、お待たせ。用って何?」
どういう風に楽しんでやろうかと考えこんでいると、タイミングよく塚本さんが扉をガラリと開けて教室に入ってきた。写真で見た通り、赤髪赤目をしたつり目がちの美少女が扉の前に立っていた。やはり気が強そうな見た目をしている。
「あぁ、塚本さん、待ってたよ」
「…え?」
親し気に話しかけた僕に驚いたのか、予想していた人物である高橋さんがいなかったことに驚いたのか、塚本さんは眉を顰めて僕の方を見た。
「誰ですか。私、夏海ちゃんと待ち合わせしてたんですが。彼女はどこ?」
塚本さんは教室内をぐるりと見渡して、待ち合わせ場所に指定されていたはずの教室内に高橋さんがいないことを確かめると、もう一度僕の方を向いて、怪訝そうに問いかけてくる。
「A組でバレーボール部の塚本詩織ちゃんだね。待ってたよ」
あえて塚本さんの質問には答えず、淡々と彼女に語り掛ける。戸惑っている様子の塚本さんとは対照的に、僕は余裕を見せつけながら畳みかけた。
「だから、あんた誰。それになんで私のこと知ってるのよ」
明らかに不快そうな表情を浮かべて、塚本さんは僕のことを訝し気に睨んでくる。この状況で強気な態度を取ってくるとは、塚本さんは確かに勝気に違いないようだ。
「僕は小林。高橋さんに頼んで、君を呼び出してもらったんだよ」
「…はぁ?あんた、夏海ちゃんとどういう関係なの。キモいんだけど」
やはり僕の口から告げられることで、ここで自分を待っていたのが高橋さんでないことが確信に変わったのだろうか。塚本さんは一層ぶっきらぼうな態度になり、僕を罵倒し始める。塚本さんは恐らく、僕のことを知らないだろうから仕方がないが、この様子だと僕の答え次第では、これ以上は話すらも聞いてもらえなさそうな剣幕だ。
「実は、塚本さんに頼みがあって」
僕を警戒した様子で扉の近くに立ったままだった塚本さんに近づいていき、素早く催眠にかける。急に距離を詰められたことに一瞬動揺したようだったが、それも催眠にかけてしまえば関係のないことだ。不審そうに歪められていた塚本さんの表情はすぐに解け、虚ろなそれに変わっていった。
「いつ見てもいいよなぁ」
先ほどまで僕のことを警戒していた女が無抵抗になるどころか、一切の感情を失くして僕の前に立ちすくんでいる。主人の指示を待つだけの哀れな人形に変わってしまった。この瞬間は、他ならない僕が、目の前の女を支配している実感を持てる瞬間だった。毎日のように女を催眠に堕として好き勝手に楽しんでいるが、この感覚は何度味わってもたまらない。
「それじゃあ、まずは…」
僕は支配欲に震えながら、眼下で揺れているオレンジ色のミニスカートをひらりと捲りあげると、清潔そうな白い下着と健康そうな太ももが丸見えになった。
「おお…」
催眠をかけてさえいれば、何をしたって咎められることはない。僕のすることは全て正しいことであるかのように、全ての女が僕を受け入れる。
「下着は白か、いいねぇ」
シミや汚れの無い真っ白な下着が、スカートの裾からちらりと覗く光景。男ならば誰だって興奮するだろう。この歳となると、子供っぽい綿生地のパンツを穿いている子もいれば、大人用のショーツを穿いている子もいて、観察するだけでも楽しいが、こういう白い下着を穿いている女も、まだ性に無頓着な感じがして悪くない。
「最高だな…」
今からこの女を僕の好きにしてもいいんだ、と有頂天になる。性的な興味など何一つ持っていなさそうな女。先ほどまで僕に嫌悪感を抱いていたであろう女。
「塚本さん、いい身体してるねぇ」
今度はスカートの裾を持ち上げ、下着を丸出しにさせる。下着は女にとって恥ずかしい部分の一つだろうに、先ほどまで僕のことを蔑んでいたであろう女が、教室で下着を丸出しにさせられて抗議の声すらも上げることはない。
「次は胸のチェックをさせてもらうよ」
僕に食って掛かっていたのとは打って変わって、塚本さんは無抵抗に立ち尽くしたままだ。その後ろに回り込んで、その胸を鷲掴みにする。制服の上から押し付けるようにして、乱暴に指に力を入れる。塚本さんの双丘は小ぶりな見た目に反して、想像以上に柔らかい。制服の上からでもわかるほどのその弾力に感心する。力を込めた指がいとも簡単に脂肪に沈んで、その形を歪めていく。
「おお…、すげぇ…」
揺らしてみたり、寄せてみたり。その柔らかな感触を様々な角度から楽しむ。下乳を揉んでみたり、上から押し潰してみたり。丁寧にアイロンの掛けられたブレザーが皺を作って卑猥な形に変わっていくのは、見ていて愉快だ。
「塚本さん、小さいけどいい胸してるんだねぇ」
制服姿の美少女の胸を好き勝手に揉むなんて、恋人同士でもない限り、滅多にできることではない。あまりにも非日常なシチュエーションに、僕はまるで痴漢をしているような気分になってくる。僕は思わず興奮して、上ずった声になりながら、塚本さんの耳元に囁いた。
「はぁ…、いい匂いもするし」
塚本さんの首筋に顔を埋めながら、気が済むまで指を動かし続ける。性の悦びを未だ知らないだろう、スレンダーな身体つき。部活の後の湿気た汗の匂いと制汗剤の香り。普段の学校生活では、女の香りをこんなに近くで嗅ぐことはない。濃厚で清潔な匂いを鼻孔の奥に取り込めば、言いようもない背徳感に襲われて背中がゾクゾクする。
「次はなぁ…」
写真で塚本さんを見たときから思っていたが、こういう勝気そうな女を侍らせるのはさぞ気分がいいことだろう。実際に塚本さんを見てから、その予想は確信に変わっていた。僕は塚本さんの写真を見せてもらったときから、彼女へのプレイ内容は決まっていた。
「じゃあ、塚本さん。いや、シオリちゃん。お前は今から僕の犬だ」
侍らせるといえば、やはり犬だろう。僕は塚本さんに向かって命令すれば、従順な彼女はゆっくりと頷いて了承する。
「…はい」
「わかったらまず四つん這いになれ。犬は四足歩行だろ」
「…はい」
虚ろな目をしたまま、シオリはしゃがみ込み、床に両手をついた。催眠に堕ちているシオリは何の躊躇もなしに、その白い手を床につけたが、教室の床は毎日掃除されているとはいえ、綺麗とは言い難い。上履きの跡がうっすらと黒く残り、毛や消しゴムのカスがところどころに散乱した不潔なフローリング。そこに四つん這いになった勝気なはずの小綺麗な美少女。本来ならば、四つん這いになるどころか、床に触れることすら嫌がりそうな塚本さんは今や、犬のシオリとなって、当たり前のように、はしたない格好をして主人を見上げている。
「犬なんだから『はい』じゃなくて『ワン』だろ」
僕は言いながら、予め持ってきていた犬耳の玩具と首輪をシオリにつけてやる。本物の犬のように扱われても、シオリは嫌がる素振りも見せない。ただ、主人の言うことを従順に受け入れて行動している。

「わんわん、わんっ」
僕の命令通りに、犬のようにワンワンと鳴いた。
「似合うじゃないか」
犬耳も首輪も、その鳴き声も。床にひれ伏した美少女が、僕だけの犬となって吠えている。つい先ほどまで僕を罵倒していた女とは思えない。生意気だったその口が、僕の言う通りに動き、吠えている。この女は、僕が支配しているんだ。僕は欲望が満たされていく感覚に歓喜した。
「そうだ、お前は犬だからな。四つん這いで歩くし、ワンワンと吠える。そして僕の命令は必ず聞くんだ」
シオリに言い聞かせるように、もう一度命令する。シオリは僕の言葉に了承するようにワンと鳴き、変わらず僕の方を見上げては次の命令を待っている。焦点の定まらない目でこちらをぼんやりと見つめるシオリに一つの提案をする。
「そうだ。犬は犬らしく、散歩にでも連れて行ってやるか」
着けてやった首輪をぐいぐいと引っ張って、シオリを教室の外に誘い出す。シオリは引っ張られている首についていくようにその脚を動かして四足歩行で僕の後ろをついてくる。
「そうだ。お前は犬だからこんな格好で廊下を歩いてもおかしくないんだ。変なことじゃないんだよ」
たとえ犬の真似がプレイの一環だったとしても、学校の廊下を歩くなど、相当なド変態以外はやろうとは思わない領域であろう。しかし、僕の犬は何の羞恥もなく、僕の後をとてとてと大人しく歩いてくる。
「そういえば、犬が制服を着ているのはおかしいよね」
「…わんっ」
僕が何を言いたいのかを悟ったのか、シオリは一鳴きして僕の声に応え、身に着けていた服を脱ぎ始めた。誰が通るかもわからない廊下。すっかり犬であると思い込んだシオリはやはり躊躇なく、身に着けていた制服を当然のことのように次々と床の上に脱ぎ捨てていく。今まで服を着ていた方がおかしいとでもいうように。
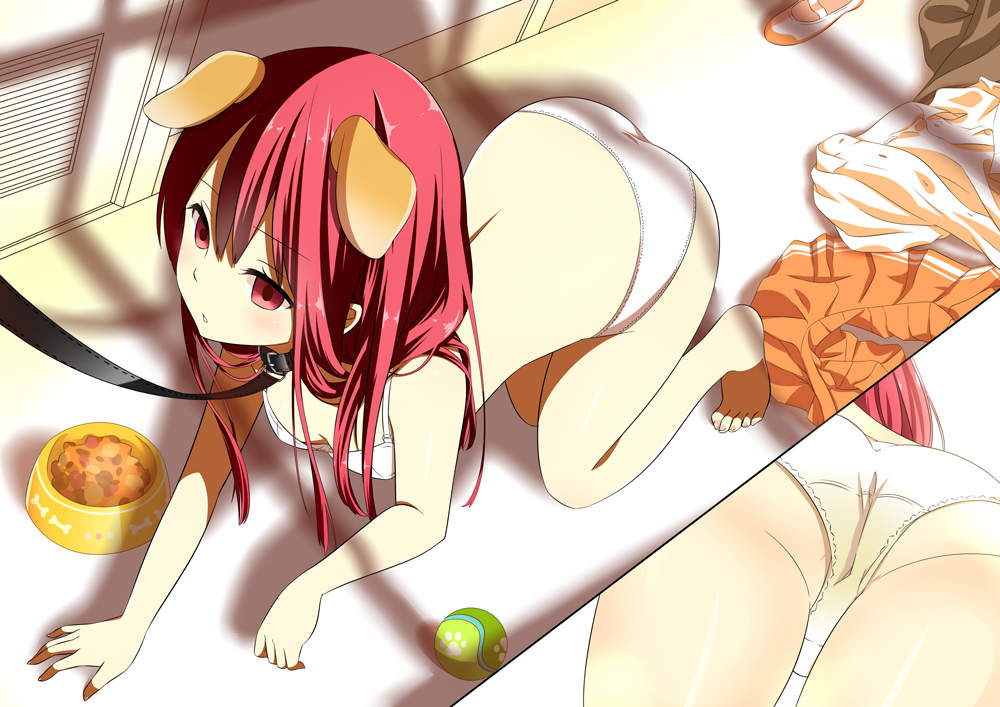
「おお、エロいな…」
靴下や上履きなど、下着以外を脱ぎ終えて、再び四つん這いになった姿を見て息を呑む。その格好のせいだろうか、白のパンツがぴったりと尻に張り付いて、いかにも柔らかそうな尻の形がはっきりとよくわかる。僕はたまらなくなって、シオリの側にしゃがみこんでその突き出された尻を撫でた。飼い主が犬を可愛がるように、ゆっくりと優しく臀部の形に沿って撫でつける。
「よしよし、いい子だぞ」
尻の割れ目に人差し指の先を添えて、秘部の割れ目の近くまで下ろしていく。
「くぅぅん…っ、わぅんっ」
シオリは触られるのがくすぐったいのか、僕の指が触れる度に身を捩っている。その様子はまるで本物の犬のようでいじらしい。
「直接触られるのはどうかな?」
今度は下着の中に無理やり手を突っ込んで、尻を揉みしだく。四つん這いという格好のせいもあってか、弾力のある尻はハリがあってずっと触っていても飽きない。そのまま、アナルの入り口に直接触れると、シオリはわかりやすいほど身体を跳ねさせる。その様子を見るに、敏感な部分に触れられて気持ちいいというよりも、くすぐったくて身体が反射的に反応しているようだ。
「くぅぅんっ、くぅん…」
僕の愛撫で快楽を感じてくれることに越したことはないが、こうやって反応があるだけでもこちらとしては愉快なものだ。僕は夢中になってシオリの身体を堪能する。
「本当に良い身体してるねぇ…、ずっと触っていられそうだ」
外気に触れてひんやりと冷えた身体が手に吸い付いて心地いい。赤子のように毛のない、白くすべすべの肌。
「下の方はどうかな…?」
下着の中に手を入れたまま、尻の割れ目から更に奥へと指を滑らせる。ぴっちりと閉じた秘部の割れ目。薄い陰唇を指先で押し潰せば、マシュマロのように柔らかい。人差し指と中指を使って陰唇を左右に拡げて遊んでみるのも妄りがましく、かなりクセになる。
「わふん…っ、くぅぅ…、くぅん…っ」
シオリは下着が擦れてくすぐったいのか、腰を振って鳴く。その腰つきは無意識ながらも男を誘惑する術を知っているかのようなそれで、僕が思わず見惚れてしまうほどであった。上下左右に細い腰を揺らめかせて、突き出した尻を動かしている様はストリップさながらだ。
「そんなにここを触られるのがくすぐったいんだ?」
そんないじらしくも淫らなシオリの姿に悪戯心が芽生え、今度は擦るように指の腹を陰唇の上で動かしてみる。
「くぅぅ…、わんわん」
そうです、くすぐったいです、とでも言うようにシオリは頷きながら鳴く。僕の指の動きが激しくなったのに合わせて、一層腰を振って僕を無意識に誘惑してくる。
「あっ。シオリちゃん、これは何かな?」
陰唇の更に奥まで手を突っ込んでやると、指先に毛の感触が僅かに触れる。背中や陰唇には毛の一本もなかったというのに、ここには僅かながら毛が生えているらしい。
「くぅぅ…」
指の先に毛先を絡めて少し遊んでみながら、ここは下着を脱がした後に存分に弄ってやろうとほくそ笑んだ。
「そうだ。何か違和感があると思ってたんだけど、犬は下着もつけないよね」
そう言いながら、下着のゴムに指をかけ、引っ張って離すと、パチンと小気味いい音が鳴ってシオリの細い腰に赤くゴムの跡がついた。きゅうん、と可愛らしい声を上げて、シオリは僕を見上げてくるが、これも躾の一環なのだ。
「何をすればいいか、シオリちゃんならわかるよね?」
「わんわんっ」
わかります、とでも言いたげな声で鳴いて、シオリはパンツとブラジャーを無造作に廊下の床の上に脱ぎ捨てていく。引き締まった綺麗な裸体が徐々に露わになり、思わず息を呑む。
「さすが運動部なだけあるね」
遂に胸や秘部が外気に晒される。つい数時間前までは生徒たちでいっぱいであった廊下。他ならぬ僕の命令によって、こんなにも従順に卑猥な姿を露わにしてくれているのだから昂らないわけがない。薄いピンクの乳首。真っ赤な秘部。僅かに覗く茂み。どの部分も惜しげもなく僕の眼前に晒されている。
「せっかく僕のペットなんだから、いいもの入れてあげる」
僕は先ほどシオリにつけてやった犬耳や首輪とは別の玩具を取り出す。今日は犬耳や首輪だけではない。僕の鞄の中には他にもたくさんの玩具を用意しているのだ。
「ほら、これだ」
鞄の中から目当ての物を取り出して、シオリの目の前に掲げてみせた。耳と首輪があるなら、しっぽもつけてやらなくてはならないだろう。そう、取り出したのは犬のしっぽを模したアナルビーズ。ふわふわの毛の先に小さな黒い球がいくつも連なったそれは、一見すれば尻の穴に挿れるような如何わしいものには見えない。文化祭の仮装にでも使いそうな可愛らしいデザインをしているのも気に入っている。
「これ挿れてやるから。ほら、もっと脚を拡げて」
僕はアナルビーズの玩具を手に持ちながら、シオリの尻を軽く叩いて細い脚を拡げさせる。そのまま小さな尻の前にしゃがみ込み、目の前の尻たぶを掴んで左右に拡げ、その奥に潜んでいる小さなアナルに狙いを定めた。
「シオリちゃん、挿れるぞ…」
シオリは恐らく尻に何かを挿れたことなどないはずだ。生まれてから10年以上の間、排泄のためだけに使ってきたであろう、無知な穴。僕はその狭い穴を無理やり拡げて、球を一つずつ押し込もうと力を込める。
「くぅぅんッ、わぅんッ、わぅぅ…」
シオリは四つん這いの格好のまま、背中を反らせながら弱々しく吠え、玩具を必死に受け入れようとしている。しかし、ビーズは小さめのサイズを用意したものの、シオリの穴は予想外に狭く小さかったようだ。そんな穴にいきなり球をいくつも挿れようなどとは存外に苦労しそうな試みだった。もちろん濡れているはずもないシオリの尻穴は、突然の侵入物にその入り口を硬く閉ざし、僕の行く手を阻んでくる。催眠をかけていてシオリ本人の抵抗はないとはいえ、身体の反射的な反応までも操ることはできないのだ。
「くっ、狭いな。ほら、もっと脚拡げろって」
よく考えてみれば、今まで排泄することしか知らなかった純朴な身体が、すぐにこんな玩具を受け入れてくれるわけもない。当然のことのように、頑なに閉じたままのアナルは中々異物の侵入を許してくれそうもない。僕はシオリの尻を叩いて、腰を上げさせ、脚を拡げさせるも、それで狭い穴が拡がるわけもない。尻たぶを一層強く掴んでビーズを力任せに押し込んでみても、球の一部が僅かに入るだけでほとんど効果はなく、初めの球の一つですら挿入することができない。
「仕方ないな…」
しびれを切らした僕は、自らの唾液をシオリの穴とビーズの両方に垂らした。濡れたビーズはヌラヌラと窓から差し込む光を卑猥に反射している。再び尻たぶを掴んで挿入を試みると、滑りが良くなったおかげか、ようやく1つ目を挿入することに成功した。つぷん、と音を鳴らしながらいかにも凶悪そうな黒い球が小さな穴に吸い込まれていった。2つ目、3つ目も同じように唾液を潤滑油にしながら挿入していく。純粋そうな女にはアンバランスな玩具が次々に挿入されていく。ビーズの球面や僕の指がアナルの壁に擦られる度に、シオリは呻き、身体をくねくねと捩る。

「きゃうんっ、わぅぅっ」
僅かに頬を紅潮させ、悩ましげな表情を浮かべるシオリ。およそ犬らしくない、ただのメスの表情だ。
「抜けないようにしっかり閉めておくんだぞ」
「わん…っ、きゃううっ」
尻を叩いて命令すれば、その衝撃でナカが振動して感じるのか、シオリはビクリと身体を跳ねさせて吠える。
「おお、少しは犬っぽくなったじゃないか」
犬種には詳しくないが、こんな犬もいるのではないだろうか。シオリは元より整った顔立ちをしているし、どんな格好をさせても似合いそうな気がする。
「じゃあ早速犬らしく、このボールを取って来てもらおうかな」
鞄の中から今度はボールを取り出す。犬用の良く跳ねるゴム状の物だ。少し転がして、取ってこいと命令すると、シオリはすぐにボールに向かって走り、口で咥えて持ってきてくれる。まるで本物の犬のようだ。
「えらいぞ、もう一回取ってきてもらおうかな」
ほら行け、と声をかけながら、今度は更に少し離れた場所に投げてみる。それでもシオリは先ほどと変わらず、従順にボールを追い、その口でボールを咥えて持ち帰ってくる。
「わふっ、わふっ。くぅん」
ボールを咥えたまま、僕の元に駆け戻ってボールを渡してくれる。
「えらいぞ、シオリちゃん!」
上手くできれば、その頭を撫でて褒めてやることも主人の仕事だ。
「よし、じゃあ次は、お手、できるかな?」
シオリの目の前に手を差し出し、合図をしてやると、迷うことなく素直にその手を乗せてくる。
「えらいぞ。じゃあ、伏せ!」
今度も大人しく伏せの格好をして、僕の方を見上げてくる。子供でもないのに、恥ずかしげもなく犬の真似をしてくれるシオリに感動すら覚える。
「じゃあ、これはできるかな?チンチン!」
まさに犬がやるように、シオリは手を胸の前に上げて座った。
「よし、よくやった。賢いシオリちゃんには、ご褒美にこれをあげようかな」
犬用の皿を取り出し、シオリの目の前でドッグフードを盛り付けてやる。たっぷりと食事を出してやると、シオリは心なしか嬉しそうな表情をしている。本当に自分が犬になったと思い込んでいるらしい。やはり僕のかける催眠の効果は絶大なのだ。
「待て、シオリちゃん。まだ食べるなよ」
息を荒げて、ドッグフードに釘付けになっているシオリを制する。お腹を空かせた犬がするように、口を開けたまま荒い息を吐いているせいで、口の端から涎が垂れている。床にぽたぽたと涎を零しながら、僕の指示を今か今かと待っている。本来の塚本さんならば、頼まれたとしても、絶対に食べたくないはずのドッグフード。それが今のシオリにとっては食べたくて仕方がない大好物に見えているのだ。
「くぅぅ、くぅぅん…」
我慢できないのか、シオリは僕の方を見上げて物欲しそうな声で鳴いている。あの勝気そうな塚本さんが、知り合いでもなかった僕にドッグフードをねだっている。僕の許しがなければ、犬の餌ですら食べることを許されない哀れな雌犬に成り下がってしまったのだ。
「はッ、はッ、はッ」
「…よし。いいぞ」
しばらく焦らした後、許可を出してやると、弾けるように勢いよく餌にかぶりついた。よほど食べたかったのか、汚い音を立てながら目の前の餌にむしゃぶりついている。
「行儀が悪いぞ、シオリちゃん」
「わうぅッ?!…くぅん」
しつけるために尻を叩いてやると、シオリは切なそうな声を上げて眉を下げた。口の周りには食べカスをつけ、餌を盛り付けてやった皿の周りにはポロポロとドッグフードを零している。まるでただのしつけのなっていない犬だ。
「ほら、ちゃんと零したやつも食べるんだぞ」
床に散らばったドッグフードを指さし、叱りつける。シオリは申し訳なさそうに一鳴きし、床に零れた餌を舐めとっていく。裸の美少女が不潔な床を必死に舐めているなんて、興奮しないわけがない。僕が興奮して息を荒げている中、何も知らないシオリは、はしたなく舌を長く伸ばして丁寧に床に散乱したドッグフードをべろべろと舐めとっていく。尻を高く上げながら頭を低くして、下品に床の上を舐めとっていく。シオリの後ろに回り込めば、陰毛が丸見えになっている。卑猥な格好だ。自分が主人に性の対象として見られていることなど露ほども知らないシオリは、腰を振りながら床を舐め、廊下を唾液塗れにしていく。
「はぁ…、はぁ…」
勝気な女がこれほどまで従順に僕の命令に従ってくれる。僕はシオリの陰部を凝視しながら、下半身を熱く勃起させていた。
「ほら、陰毛が丸見えだぞ」
僕は陰部の先で茂った毛を指先に絡め、もう片方の手で陰部に人差し指の先を突っ込んでかき回す。
「あまりはしたない格好してると、こうやって雄犬に襲われるからな」
薄い毛の中に指先を突っ込んで弄ぶ。濡れていなかった陰部も少しずつ濡れてきているのがわかる。
「くぅんッ、わんッ、わんッ!」
しかし、シオリはといえば、腰を振りながら与えた餌に夢中になっている。頭の中はドッグフードのことでいっぱいのはずなのに、身体は僕の愛撫に反応しているらしい。全く淫乱な雌犬だ。
「わんッ、わぅんッ!はぁッ、はぁッ!」
いつの間にか皿の中は空になってしまっていたらしい。しかし、食べ終わってもまだ足りないのか、シオリは何も残っていない皿の内側や廊下の床を舐めたり、舌を口の隙間からだらりと垂らしたりしながら息を荒げている。
「シオリちゃん、そんなにこのドッグフード気に入った?」
シオリはもっと欲しいとでも言うように、勢いよく頷いている。
「今度また持ってきてあげるからね」
僕が笑いかけてやると、シオリは嬉しそうな鳴き声をあげた。
「シオリちゃん、そろそろおしっこしたくなってきたんじゃない?」
僕が問いかけてやると、シオリは小さく頷いた。普段は我慢できるぐらいでも、催眠をかけてやれば、出したくさせることもできる。自分は尿意を催しているんだ、と暗示をかけてやればいいだけのことだ。
「犬がするおしっこは見たことあるでしょ?じゃあ、どうやってやればいいかはわかるよね?」
人間のように出させるのもいいが、せっかく犬の格好をさせているのだ。犬のように脚をあげたポーズではしたなく放尿してもらってじっくり観察するとしよう。

「わんっ、わん…、わふっ」
シオリは僕の命令に従って、犬のように放尿しようと、左脚を上げた。眉を顰めて目を瞑っている表情を見るに、力を込めているようだ。しかし、中々陰部から尿が出てくる気配はない。
「シオリちゃん、がんばれ」
慣れない体勢に筋肉を使い慣れていないのか、身体が僅かに震えている。片脚を上げたまま、下半身に力を入れていては、そうなるのも仕方ない。それでもシオリは僕の命令に応えようと踏ん張っている。
「くぅぅ…、くぅん…」
踏ん張ってはいるものの、やはり思うように出てくれないらしい。
「もうちょっと踏ん張れ、シオリちゃん!」
健気に頑張っているシオリを応援する。しばらく見守っていると、黄色い雫が一滴ずつ零れ始めた。
「う…、あぁ…」
これは決壊寸前だ。シオリの陰唇の奥が開き始めたのが見えた。
「うぅ…、あぅ…っ、わんっ、わぅん…っ」
悩ましげな声を上げたかと思えば、次の瞬間には黄色の液体が勢いよく放物線を描いていた。シュイイイ、と小気味いい音を立てながら放たれていくシオリのおしっこ。外気で身体が冷えていたのか、放出された尿は湯気を立てて、廊下を次から次へと汚していく。
「よく見えるな…」
僕はシオリの後ろに回り込み、シオリが犬のようなおしっこをしている様子をじっくりと眺める。脚を上げているおかげか、陰唇はぱっくりと開き、おしっこが漏れ出している場所がよく見える。放尿するまでは苦労したものの、シオリ自身かなり溜まっていたらしい。勢いはしばらく衰えることはなく、シオリの下に大きな水たまりが作られていく。
「あ…ッ、わんッ、わんッ!」
シュイイイーッ!じょろじょろ…。水たまりに尿が跳ねて飛沫となり、辺りにもたくさん飛び散っていく。
「あぁ…、くぅん…っ、はふ…っ」
チョロチョロ…。気持ちよさそうな表情をしながら放尿をしている美少女。勢いは段々と弱まっていき、その太ももを伝いながら床へと零れていく。
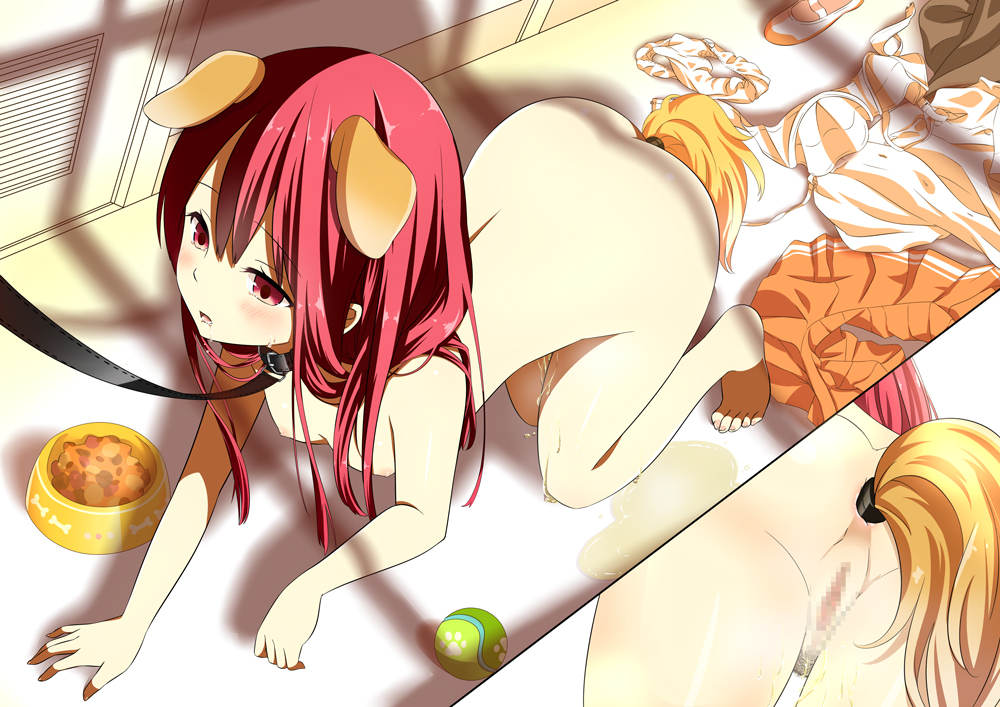
「わん…っ、わふん…っ」
開放感に満ちたような快楽の表情。身体全体を震えさせながら、放尿しているはしたない姿。
「あ…っ、あ…っ!くぅぅん…っ」
まるで絶頂でもしたかのような蕩けた表情。
「わん…っ、わぅんっ」
「全部出せたのか?えらいな」
ようやく全部出し終わったのか、脚を元の四つん這いに戻し、惚けたように虚空を見つめるシオリの頭を撫でてやる。
「それじゃあそろそろ、これも抜いてやるか」
時計を見ればいい時間だった。アナルに挿したしっぽの毛を掴んで揺らしてやると、シオリは顔を赤面させて喘ぎ声のような声を上げている。
「待てよ、自分でひり出す方が面白いか」
アナルで感じ始めているのか、やけに反応がいいところを見ると、自分で踏ん張って出して欲しいと思ってしまう。僕が無慈悲に一気に引き抜いてやっても良かったのだが、今回は自分で出してもらおう。僕はシオリに、自分で出してみろ、と命令した。
「う…、うぅん…、わんっ、わぅんっ!」
先ほど放尿したときのように、シオリは腹に力を込めて、気張っている。
「まだまだ足りないぞ、シオリちゃん。もっと力入れろ」
腹筋が足りないのか、アナルビーズはまだびくともしていない。
「ふんっ、ふぅんッ!」
僕の応援に応えようと必死に頑張っているシオリの姿に庇護欲を掻き立てられる。
「ふんッ、ふぅぅんッ!くぅぅんッ!」
勢いよく力を込めたと同時に、ぽんっ、と一つ目のビーズが飛び出してくる。
「おお、頑張れ、シオリちゃん!」
「ふんッ、わんッ、わんッ!」
今度は力んだ勢いと同時に残ったすべてのビーズが飛び出してくる。ぽんぽんぽんッ、と次々に小さな穴から球が出てくる様は、、美少女にはあまりに不釣り合いで興奮する。
「あ…、あぁ…っ!」
シオリはアナルビーズをひり出す感覚に快楽を感じ取ったのか、ゾクゾクと震えながら口を開けて喘ぎ声のようなものを上げている。
「あぁ…っ、うぅ…」
ぼとっ、とアナルビーズが床に落ちる。シオリはあまりの衝撃にイってしまったらしく、床に上半身をつけた体勢で、身体をビクビクと跳ねさせている。
「あぁ…ッ、あぁ…」
アナルで絶頂する女というのは、下品でそそるものがある。その上、催眠をかけていれば、女には恥も外聞もなく、ありのままの姿を曝け出して絶頂している姿を見せてくれるのもいい。
「さて、汚したものをそのままにするわけにもいかないしな」
床についた唾液ぐらいなら放っておけば明日にでも渇いているだろうが、これだけ大量の尿で濡らしてしまっていては、そうもいかない。それに、シオリの身体もびしょびしょに濡れていて、このままだと風邪を引いてしまうかもしれない。キョロキョロと辺りを見渡して、僕の目に入ったのはシオリの穿いていたパンツだった。
「ちょうどいいところに拭けそうなものがあるな、使わせてもらうよ」
僕は落ちていた白い下着を拾い上げる。それを使って、シオリの身体を拭いていく。股の間や太もも、膝。かなりの量を出したせいで尿の池に浸かっていたらしい足の先まで拭いてやるはめになった。
「ふぅ、こんなもんか」
一枚のショーツで拭くにはシオリの身体は濡れすぎていて、完璧に拭き取ることはできなかったが、及第点だろう。
「床も適当に拭けば大丈夫だろう」
既にびしょびしょに尿を吸い込んだ下着で床を拭きとっていくも、ほとんど効果はない。せいぜい池になっていたものを塗り広げるぐらいだろう。
「まあ、監視カメラが付いてるわけでもないしな」
多少塗り広げておけば、蒸発もしやすいだろう。もし、明日になって濡れたままでも、誰が犯人かなんてわかるはずもない。それに、まさか廊下におしっこが零れているなんて思いもしないはずだ。
「だいぶ濡らしちゃったけど、穿けるよね?」
シオリにびしょびしょに濡れた下着を手渡すと、嫌な顔一つせず、脚を上げて穿き始めた。水分を吸収して重たくなった下着がシオリの腰まで持ち上げられていく。その途中にも、ぽたぽたと水滴が零れていき、床に新たな水たまりを作っていくが気にしない。普段の位置まで持ち上げられ、肌と下着が密着すると、ぐちょ、という水音がする。
「じゃあ、さっき脱いだ制服も着ていいよ」
床に無造作に散らばっていた制服などを指さして命令する。
「はい…」
シオリは自分の脱いだ服を拾い上げ、ゆっくりと身に着けていった。
「そうだな、僕たちはあれから偶然気が合って、楽しく話をしたんだ」
催眠をかけたときは、その後の記憶の改ざんも重要だ。催眠にかかったときの記憶は基本的には残っていないが、催眠が解けた後に、催眠にかかる前との時間のギャップが生まれてしまう。今回であれば、塚本さんが僕と教室で嫌な出会いをしたことは覚えていても、その後の数時間の記憶がなくなってしまうのだ。
今回の場合は、楽しくおしゃべりをしたことにしておけばいい。若干無理があるような気もするが、まあ大丈夫だろう。僕と教室で話していただけで下着がぐっしょり濡れているはずもないが、それは僕の知ったことではない。僕はシオリの催眠を解いてやり、先にその場を立ち去った。
「次も別の女に紹介してもらった女にしようかな」
勝気な女を侍らせるのはやはり気分がいい。今回は挿入までしなかったので、次も塚本さんを呼び出してセックスまでしてみるのも悪くないかもしれない。また同じく犬の暗示をかけて、獣のようなセックスをするのも楽しそうだ。
「あ、高橋さん。ちょうどいいところに」
帰り際に塚本さんを紹介してくれた高橋さんに偶然出くわした。そういえば、今回はセックスをしていないどころか、射精すらしていないな。
「そうだ、高橋さん、今から時間あるかな?」
近づきながら、催眠をかける。一度催眠にかけた女は催眠に堕ちる感覚を覚えるのか、次に催眠にかけるときには そう苦労しないのだ。
「はい…」
返答する暇も与えない。高橋さんが発する一言目は既に催眠に堕ちた後だ。許されるのは肯定の言葉だけだ。さっきシオリに使ってやった玩具を高橋さんにも使ってやるのも面白いかもしれない。
「高橋さん、君は犬だよ」
先ほど塚本さんにかけた催眠と同じ暗示をかけ、公園に誘い込んだ。
「これだから催眠はやめられないな」
僕はほくそ笑んだ。
